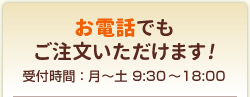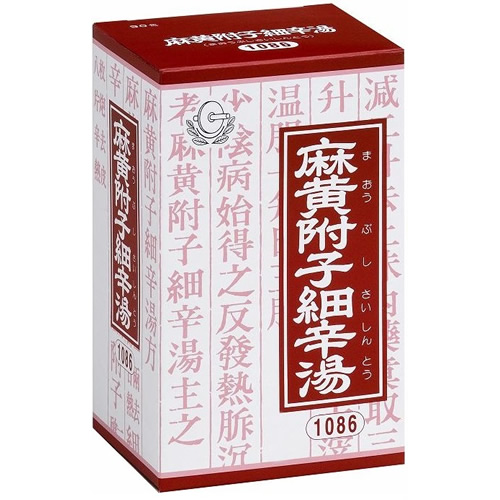- ナガエ薬局
- [特集]秋の花粉症に効く!漢方薬特集
秋の花粉症に効く!漢方特集

粉症は春の杉花粉だけではありません。
8月~10月に発症する秋の花粉症は、キク科のブタクサやヨモギの花粉がアレルゲンとなっています。他にもシラカバやイネ科の植物などで症状が起きる方もいます。
その他の秋の特集はこちら
花粉症の原因とは?
花粉症の4大症状!
花粉症の4大症状とは、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみといわれています。くしゃみ、鼻水、鼻づまりはアレルギー性鼻炎、目のかゆみはアレルギー性結膜炎で、体内に入った花粉を輩出しようとして症状が起こるものです。症状の程度は個人差があります。

アレルギー性鼻炎増加の原因
アレルギー性鼻炎に悩まされる人が、近年急増しているといわれていますが、その原因としては次のようなことがあげられます。

アレルギー性鼻炎のメカニズムと注意点

アレルギー性鼻炎が起こるメカニズムは、ホコリの中に含まれるダニの死骸やスギの花粉が体内に入ると、抗原抗体反応が起こります。するとある種の細胞から化学物質が粘膜内に出て、この化学物質の刺激によって、鼻の粘膜の自律神経の働きのバランスが乱れます。このため、くしゃみが出たり、鼻の粘膜の血管が拡張しすぎて鼻詰まりを起こしたり、水のような鼻水が多量に分泌されたりします。
アレルギー性鼻炎を起こす抗原の代表的なものは、ハウスダスト(室内のホコリ、綿、絹、化学繊維、羊毛など、ペットの毛、室内のホコリの中に含まれるカビやダニなど)と風媒花(スギ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギなど)の花粉です。花粉によって起こるものを花粉症といいますが、たとえばスギ花粉症は春先、ブタクサは秋というように、アレルゲンとなる花粉の飛ぶ季節と一致するのが花粉症の特徴です。
アレルギー症状を軽減するには?
「衛気(エキ)」を強化する事が症状改善へ繋がります
中医では、生活環境が人体に与える影響を非常に重視しています。気候の変化が異常な場合や、人体が抵抗力を無くした時には、風邪・寒邪・暑邪・湿邪・燥邪・火邪(熱邪)という六淫が病気となって人体に障害を与えます。中でも、花粉症の外邪(アレルゲン)は「風邪」です。
8月~10月に発症する秋の花粉症はキク科のブタクサやヨモギの花粉がアレルゲンとなっています。他にもシラカバやイネ科の植物などで症状が起きる方もいます。中医学では、ウイルスや細菌、花粉などの外敵から身を守り、侵入を防ぐ役割を果たすバリアを「衛気(エキ)」と呼んでいます。現代人に増加している花粉症やアトピー、喘息などの症状改善には、外敵を寄せ付けない「衛気」を強化することがポイントです。
また、花粉症は衛気不足・水飲・外邪の三要素によって発症します。衛気不足や水飲(水分代謝機能の異常などによって生じた、病理的な水分)も肺・脾・腎の陽気不足によって生じますが、飲邪の性は寒であるため、少量の生冷飲食によっても容易に誘発されます。体を冷やすことによって免疫力が落ちるというのはこのメカニズムによるものです。また、衛気不足は気の免疫不足によって生じます。呼吸や消化、免疫などの機能や役割をする、肺・脾・腎を元気にすることが衛気のパワーアップにつながります。
秋は春よりも痰湿を抱え込んでいる人が少ないから秋の花粉症が話題になりにくいのかもしれません。しかし、私たちを取り巻く環境は意外と体を冷やす状態にあるようです。飲食・生活環境を気にしながら養生をしていく必要があります。

アレルギー性鼻炎に効く漢方薬
症状が出たらまずこちらがオススメ
花粉症のファストチョイスの漢方薬です。くしゃみ、鼻水、つばが多く出てうすい痰などの症状にとっても良く効きます。
体力のない方や冷えが強い方に
くしゃみが何回も出る・涙が出る・うすい水のような鼻水が流れるように出る・背中が寒くぞくぞくするなどの症状に効果があります。
長引く胃炎・鼻づまりに効果があります
寒い時期にくしゃみや鼻水が治まっても、鼻づまりだけが残ってしまう鼻炎には最適です。長引いて慢性化した鼻炎。蓄膿症にも効果があります。鼻水は粘りのある鼻汁が適しています。
鼻づまりが顕著で鼻水が無い方に
鼻炎が慢性化してしまった状態で葛根湯加川芎辛夷でも効果がいまいち見られない方におすすめの漢方薬です。鼻も乾燥が強く、熱感がある鼻づまり、臭いが判別しにくいなどの症状にもおすすめです。
慢性鼻炎・蓄膿症の改善に
鼻水、鼻づまり、頭痛、頭重感、副鼻腔の圧痛、鈍痛などの症状がある方に。鼻づまりの強い慢性鼻炎や、濃い鼻水の出る蓄膿症・鼻づまりに効果があります。
不安感・動悸・めまい・ふらつきのある方に
朝起きにくい、急に立ち上がるとめまいだけでなく動悸もする、頭に何かをかぶっているようにぼうっとする、むくみっぽい様な人に使用します。